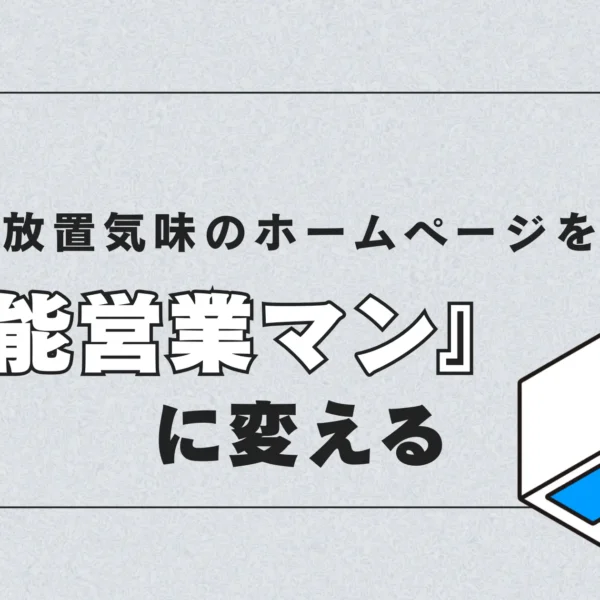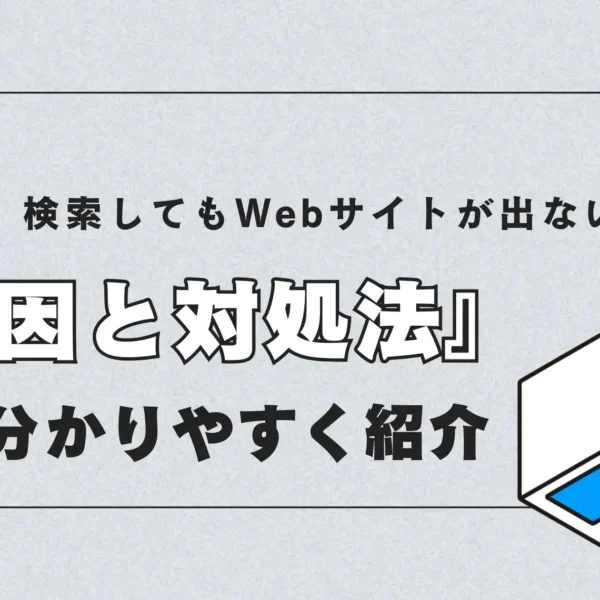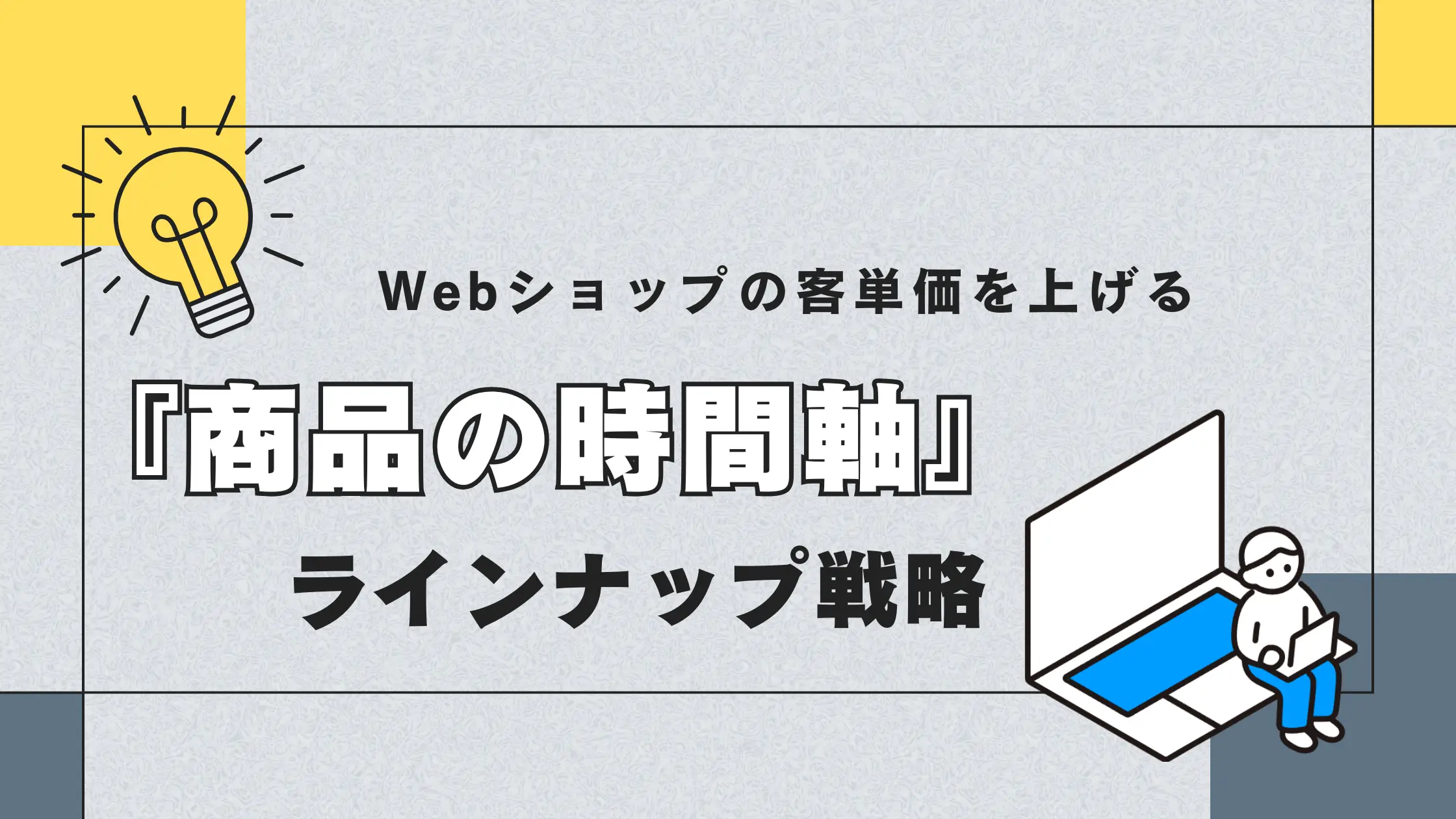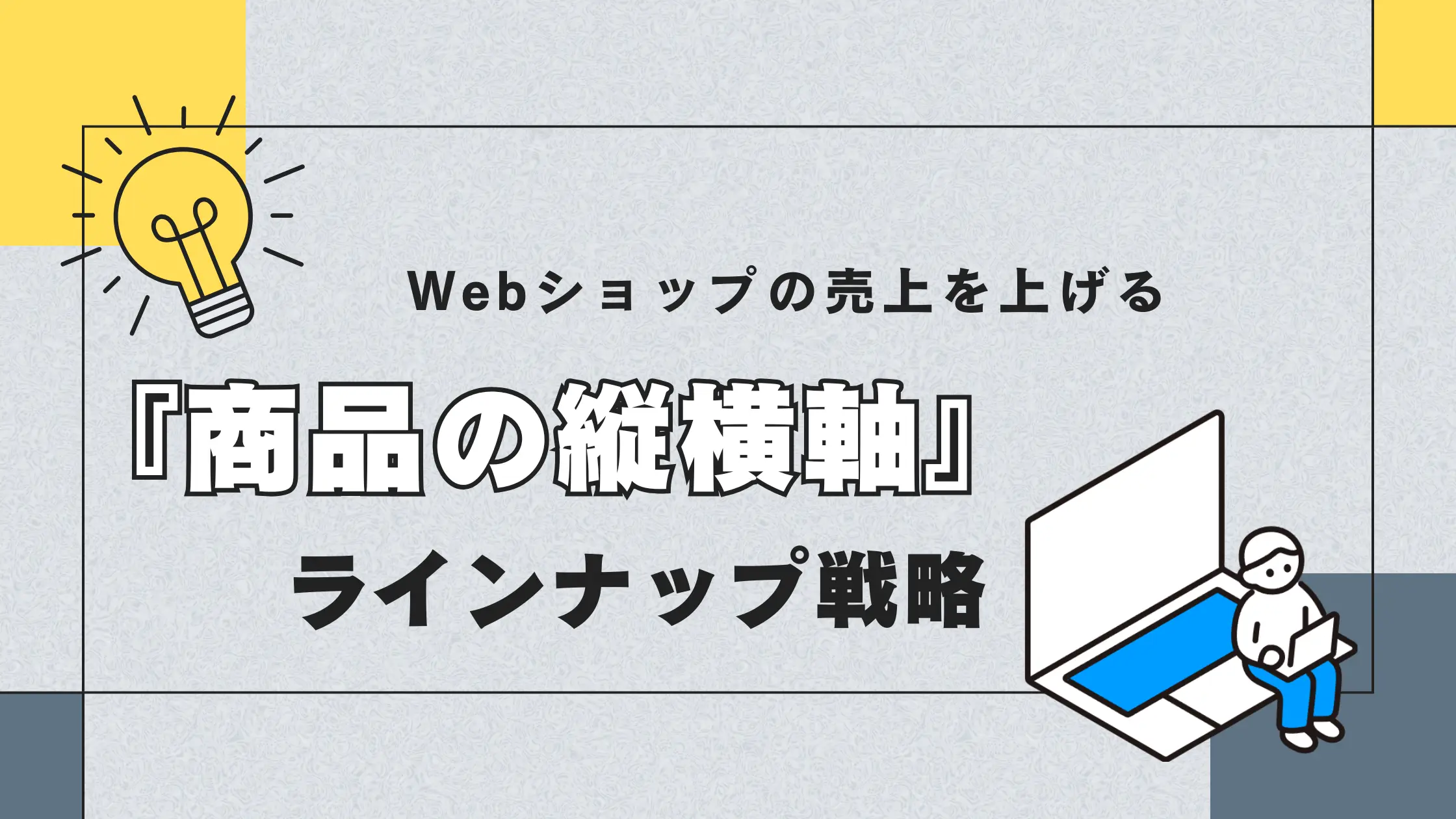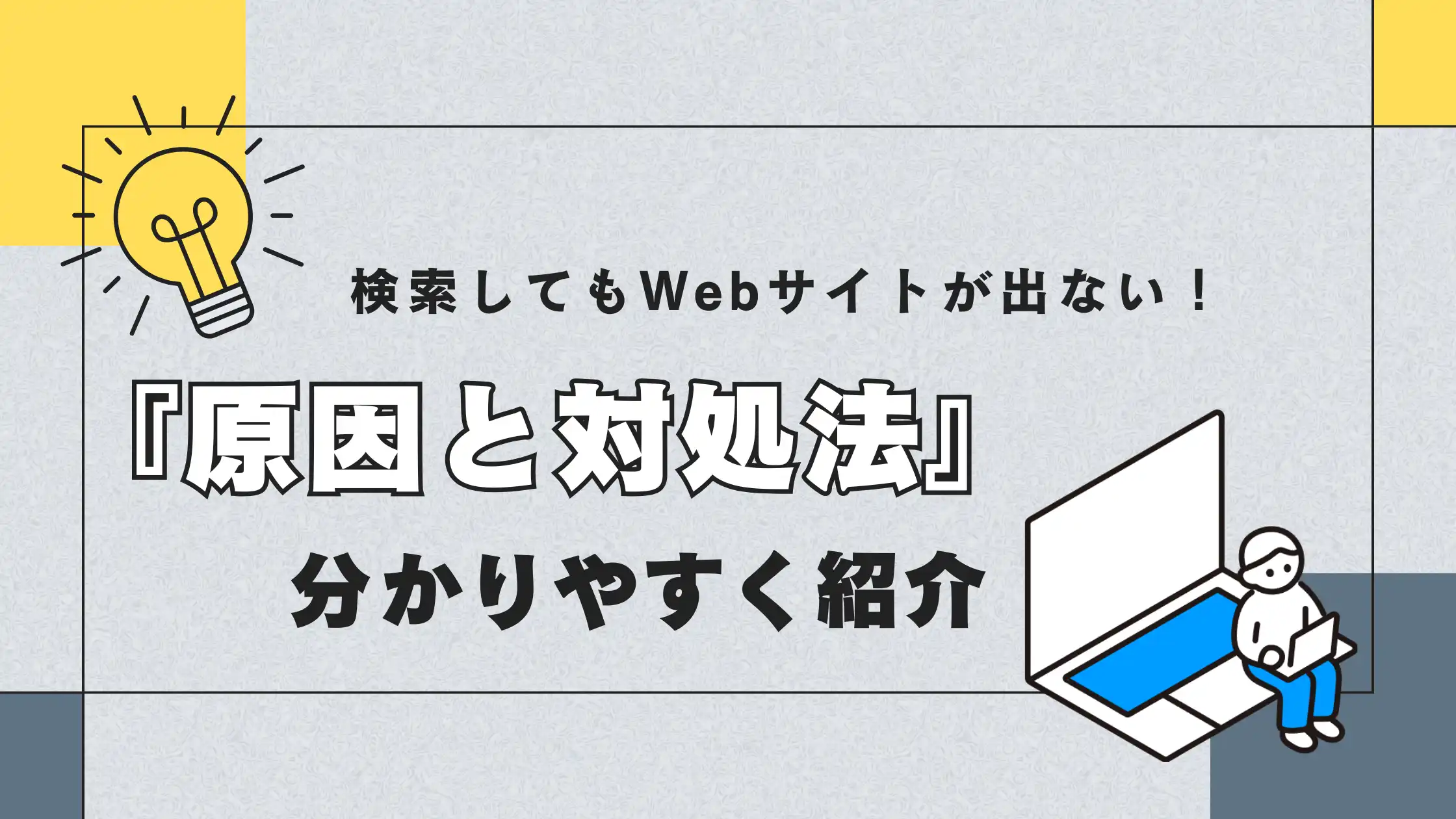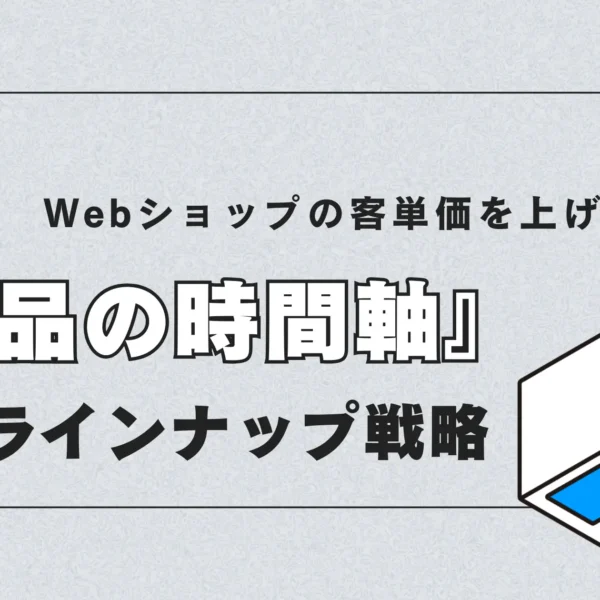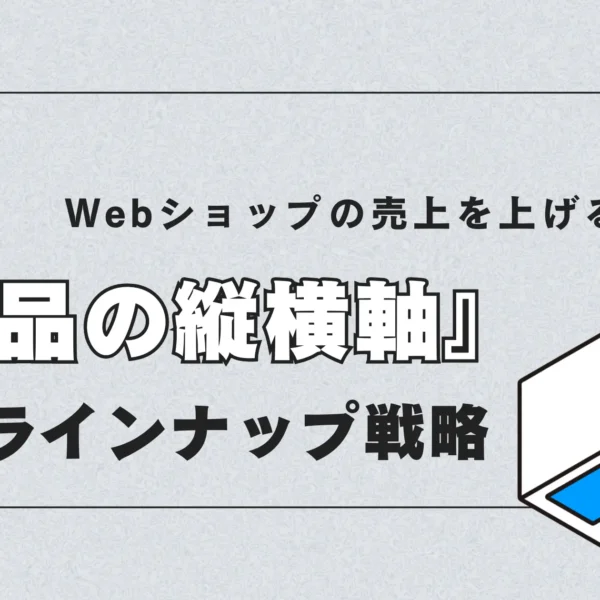「ハローワークに求人を出してるんですけど、もう何か月も採用の応募がゼロで…」
私のようにウェブサイトのコンサルティングなどで、お客様とよく接する立場だとこういった切実なご相談はよく受けます。特に地方は企業・店舗での人材確保の課題は強いです。
(お客様のご要望に応えてスキマウェブが採用周りの支援も行っている理由のひとつでもあります)
会社や店舗から求人応募を出しているのに「何故か」問い合わせすら来ない。このままでは事業計画だけでなく、現状の穴埋めですら難しい…
「良い人がいれば新卒や中途を問わず採用したい」のに、そもそも応募がこなくてスタートラインにすら立てない状況は本当に焦りますよね。
「今は時期が悪いだけ、待っていれば解決する」
応募がこないことが時間で解決するような原因だったら今後が期待できますが、採用に課題がある方を色々見てきた身としては、基本的に放置で改善しない方が大多数でした。現状が悪いのなら、手を打って変化を生まない限り良くなりません。
放置が悪い理由として、あなたの競合他社は保留せずに動いているからです。悪い状態で手も打たずに待てば待つほど、人材獲得で競合にどんどん差をつけられてしまいます。
ウェブサイトのコンサルティングや採用支援を経験してきた者として、何故あなたの会社・店舗の求人に応募が来ないのか、その根本的な原因を解説して、明日から取り組める具体的な解決策を3つのパターンに分けてご紹介します。
採用活動の新たな一歩を踏み出すヒントが見つかればと思います。
【結論】応募が来ない現状は、施策の打ち手で解決の確率を高められます
採用応募が来ないという根深い悩みは、改善できる可能性が高い課題です。
重要なのは応募が来ない「原因」を正しく理解して、自分に合った施策の「打ち手」を選ぶことです。
現状を放置すれば理想の人材に出会えるどころか応募自体も増えず、いつまで経っても求職者に選ばれる側になれません。
ただし、採用はマーケティングにも言えますが「これをやれば100%応募が来る、理想の人材が採れる」という魔法はありません。
いずれも現状から確率を高めていくための施策ですが、動いたからこそ応募の確率が上がって採用につながっていきます。
ぜひ原因を理解して、正しい方向性の施策を検討してください。
応募数が増えてくれば、会社に合った求職者と会える機会も増えてくるため、会社の成長につながる効果的なリクルートの実現は夢ではありません!
それでは実際に応募が来ない原因を解説していきます。
なぜ応募が来ない? 放置で解決しない理由
私は経営コンサルタントではないため、募集要項の条件を良くするための経営改善などは行わない、現状の条件面を踏まえての解説となります(給与や3K環境といった構造以外の課題という意味です)。
応募が来ない主な原因は『求職者への露出不足』、『応募率を阻害する要素』です。
もう少し細分化すると以下の3つに分けられます。
そもそも求職者にあなたの求人が「見られていない」
- ターゲット層が見ていない求人媒体に掲載している。
ハローワークへの無料掲載、たまに新聞などに求人広告を出しているレベルはアウトです。そもそもですが現代の求職者はネットで求人を調べるのが標準です。
求人情報が検索できるindeedやAirワークのようなウェブ採用サービスに求人を出稿しないと、まず見つけてもらえません。極端な言い方ですが求職者からすれば、ウェブ上で見つからない=存在しない会社・店舗です
- 公式に採用情報が載っていない。
運良くあなたのWebサイトに訪問されたとします。
採用に関する情報が載っていなければ、求職者は「いま募集しているのか?」と不安になって応募の検討が鈍ってしまいます。
求職者はindeedなどで多くの募集を見て条件などを比較します。そこで、次の情報収集先として選ばれるのが公式のWebサイトです。
この時点で社名や店舗名で検索してWebサイトが見つからなければ、実在性を疑われて応募はさらに鈍ります。
求人を見られても「魅力が伝わっていない」
- 給与や待遇といった条件面ばかりで「生きた情報」が伝わっていない。
「求職者が働きたい会社に求めること」というあるアンケートでは、意外かもしれませんが仕事などのやりがいが1位と出ています。
必ずしも給与や福利厚生が1位ではないわけです(もちろんアンケート上位に入る項目ですが)。
それでは今の募集要項やWebサイトに、やりがいを想起させるような情報は載っているでしょうか?
- 採用サイトや掲載情報が古い、求職者が「応募したい」と思える状態になっていない。
現代の求職者の大多数はスマホで情報収集をしています。そのため、スマホで見たWebサイトのデザインが崩れて可読性が悪かったり、明らかに古い写真・内容を使っていると、見た目の印象から就職先に対する不信感が生まれてしまいます。
また、何度も変更するのが面倒と、募集要項は最低限の情報しか載せてないでしょうか? 情報が少なすぎると求職者が不安になって応募のハードルが上がります。
応募への「ハードル」が高い
- 応募が複雑すぎる。
ピカピカの採用サイトがあっても、応募フォームの入力項目が多すぎれば送信率は低下します。
会社の方針なども関わるので一概に言えませんが、応募時点での履歴書や職務経歴書の添付が必須になっていれば当然、応募ハードルが上がって応募率が悪化します(応募時点でのスクリーニングにもなるので否定していません)。
- 会社の雰囲気が分からず、求職者が応募に不安を感じてしまっている。
求職者にとって就職は人生に関わる非常に大きな決断です。そのため、応募前段階での情報収集はかなり広く深いものになります。
せっかく良い条件で募集を出しても、仕事内容や会社の雰囲気、既に働いている人たちの生の情報が得られなければ「待遇の良さにウラがあるのでは…?」といらない不信感を与える可能性があります。
これらの課題を放置するリスクは、あなたが考えている以上に深刻になっているかもしれません。何故なら競合他社は既に、WebやSNSを駆使して自己アピールを行っている可能性が高いからです。
このまま何もしなければ、人材獲得競争はますます不利になり、今だけでなく将来生まれる求職者もライバルに奪われてしまう可能性が高いです。
「何か手を打たないと、本当にマズい…」
「でも、具体的に何をどうすればいいのか分からない」
そんな風に感じているなら、ぜひ次の解決策を参考にしてください。
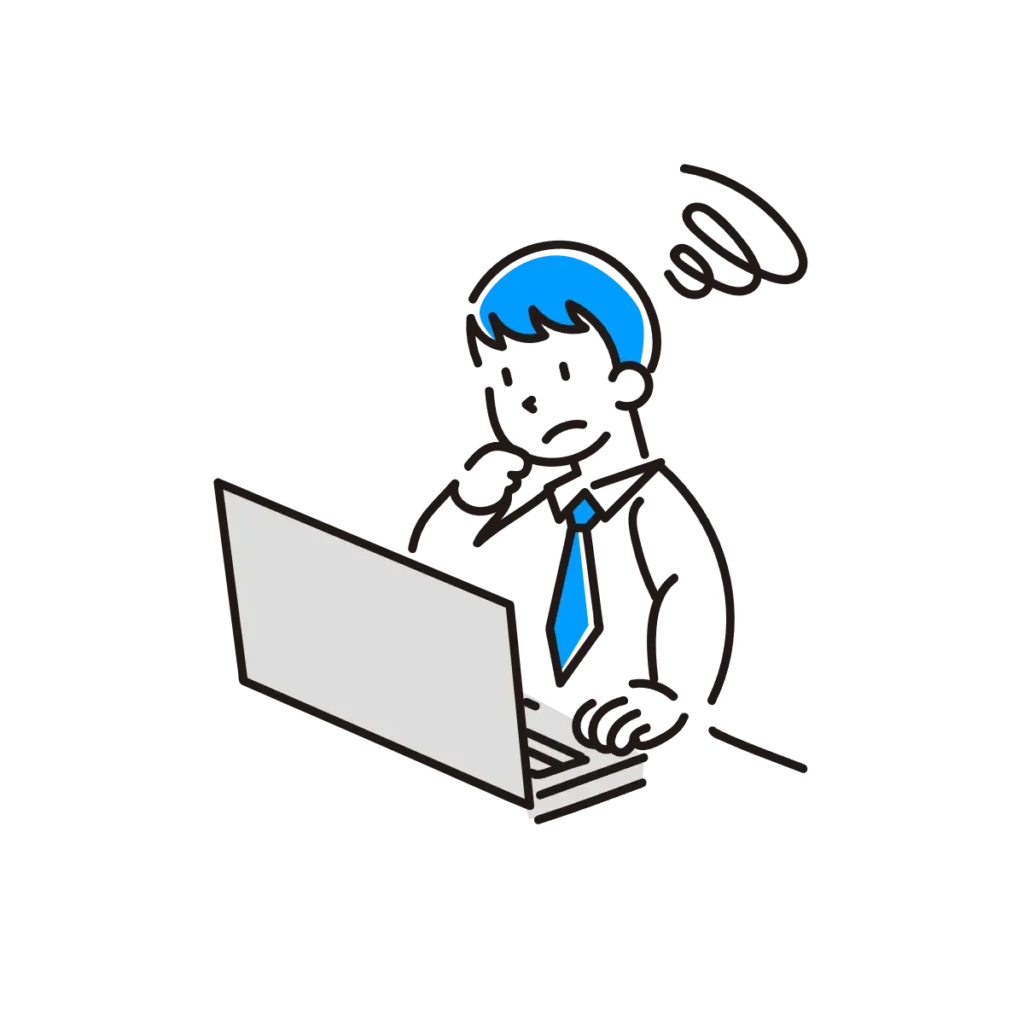
【具体策】コストと手間で選べる3つの解決方法
ここでは予算やかけられる手間別に、3つの解決策をご紹介します。
いずれも一長一短ですが、短期または長期的な目線や、専門性の高いスキルを持つ人材がピンポイントで欲しいなどで、手法のコスパも変わります。
1. 大きなコストを払ってでも、即効性を求める方法
求人へのコストを覚悟した企業が取る、確実性の高い手法です。
人材紹介サービスでは専門性の高いスキルを持つ人、実務経験者を狙い撃ちにしたマッチングがしやすいのが特徴。
求人のWeb広告を打つことで、採用に受動的な層への認知を広げたることも可能です。広報という目線で言えば会社自体の宣伝も一定の効果があり、会社を前面に出すことで求職者が認知すれば、就職・転職時の候補として上がる確率が増えます。
- 手法
人材紹介エージェントの活用、大手求人媒体の上位有料プランへの掲載。
(例:リクルートエージェント、マイナビ、doda)
スカウトサービスを使って、自分で登録された人材から良さそうな相手にコンタクトを取る方法もあります。
(例:ビズリーチ、Wantedly、Green)
indeedに有料広告を出して募集情報が見られる回数を増やす、プレスリリースなどを会社やサービス・商品の宣伝は、求職者への認知度を上げる目的で有効です。
- メリット
人材紹介会社はこちらの要望に合わせて候補者を探してくれるため、自分から良い求職者を探す手間が大幅に減らせます。
また、人材紹介系は登録求職者の数が多い=市場が大きいことから、短期間でマッチング・採用できる可能性が高いです。
私が会社員時代に採用も担当した個人的な経験で言えば、人材紹介からの求職者は高いスキルや実務経験があるなど、能動的に応募してくる層より即戦力として期待できる人材が多い傾向がありました。
- デメリット
これも会社員時代に自部署の採用も担当した経験からの所感ですが…デメリットはコストが非常に高額なことです。
例えば年収400万円の人材を中途採用した場合、成功報酬として約120万円(年収の30%が相場)の手数料が発生します。しかも、その方が定着する保証がありません。もし早期に退職してしまったら、非常に買い物になってしまいます。
加えて、人材紹介会社は採用時の成約金が自分の報酬になるため、報酬欲しさで会社に合っていない不適切な人材を紹介される傾向がかなりあります。
有料広告も継続的な運用には月辺り数万~数十万掛かるうえ、応募が約束されるわけではありません。プレスリリースも費用が掛かりますが、よほど求職者に関係のある話題でない限りは地道な知名度上げの期間が必要です。
2. コストを抑え、自分の手で解決する方法
時間と労力を武器に、コツコツと自分たちで取り組む手法です。
社内人員を確保して長期的に取り組めるのなら、イニシャル・ランニングコストをコントロールしやすく、コスパの良い結果が期待できる可能性があります。
ただ、各種採用媒体の管理、採用目線での自己アピール、社内体制の見直しなど、見えている以上に負担が発生する可能性が高いです。
- 手法
ハローワークなどの求人票の見直し、SNSを使ったネットでの自己アピール、ウェブ応募ができる求人サービスの活用、自社サイトへの社員インタビューの掲載など、やり方は多岐にわたります。
社内体制や制度づくりが可能なら、リファラル採用(社員などからの紹介雇用)や、アルムナイ採用(退職者の再雇用)なども視野に入ります。
- メリット
CMが頻繁に打たれて知名度の高い、採用検索エンジンのIndeedは無料で使えます。
こうした採用サービスへの登録・求人出稿を自力で行えば、長期的に無料で利用しつつウェブからの応募創出が狙えます。
また、ネットで調べれば、求職者に向けた自己アピールの仕方などが掴めるため、それを参考に既存の採用フローの見直しや、情報発信の強化などを自社のリソースで行えれば工数のみに抑えられます。
- デメリット
自社に合った手法の調査をした上で、社内人員の工数を確保して採用計画の実行と運用まで行うため、学習コストだけでなく運用中もコストが掛かります。
また、自力でノウハウを探すことから、成果が出るまでに時間が掛かることに加えて、アプローチを間違うと工数を掛けたのに結果も出ないという最悪のパターンもありえます。
ランニングコストの一例とあげると、新卒や中途採用のために週に3回SNSで投稿するとします。
ネタ探しや文章作成、画像準備に1投稿あたり30分だと、月間で約6時間の工数になります。兼業する場合、当事者の生産性が採用への注力次第でさらに下がります。
3. Web制作会社に相談して提案をもらう方法
専門家の知見を借りて、効果的に課題解決を目指す手法です。
Web制作会社と言っても得意としている領域が会社ごとに違うため、提案内容もコスト感もかなり幅があります。
Webサイト制作のみを得意とするところだと、立派な採用サイトは作れても、それ以外の応募導線や応募率改善などのアドバイスまではもらえないかもしれないため、相談先の検討も必要です。
- 手法
Webサイト制作をメインとするところであれば、採用専用Webサイトの制作や、採用に特化したWeb広告の運用や持続的なウェブ採用方法の提案が期待できます。
採用のコンサルティング、マーケティングを得意とするところであれば、求職者を惹きつける募集要項の作成代行や、Indeedなどの採用プラットフォームの導入支援を請け負ってくれます。
(ちなみにスキマウェブでは採用サイト制作から、採用プラットフォームの導入、求職者の反応率を上げるための募集要項の作り込みなどが可能です)
- メリット
ウェブからの応募獲得という目的に対して、専門知識に基づいた効果的な施策提案が期待できます。
依頼先によっては採用活動の一部業務を任せることで(募集要項の出稿など)、あなたは本業に集中して採用応募があった時だけ対応といった分業も実現可能です。
採用を得意とする制作会社であれば、長期的運用に耐える仕組みの提案もしてくれるかもしれません。
- デメリット
当然ながら、外部への依頼コストが発生します。
ただ、人材紹介会社に対して採用1名・100万前後の紹介手数料を考えれば、施策によっては対費用効果が高く長期的な効果が期待出来る場合があります。
(例:100万で採用サイトが作れる、1年間の運用代行費用がまかなえるなど)
また、ウェブの採用だからと、すべての制作会社が採用に強いわけではありません。Webサイトのみ作れるところや、マーケティングだけに対応する会社も珍しくないため、ウェブ採用に関する記述を見掛けたら問い合わせが一歩目となります。
【具体的な事例】
【まとめ】一歩踏み出すから応募が生まれます
採用応募が来ない問題は、現状を見て見ぬふりをせず、行動を起こすことで解決の糸口が見つかります。
紹介した3つのアプローチの中から、取り組めそうなものがないか検討してみてください。
そして、最初の一歩は自社の採用活動のどこに問題があるのかを客観的に把握することです。
「何から手をつければ良いか分からない」
「自社に最適な方法を客観的に教えてほしい」
と感じたら、抱え込まずにプロに相談してみるのが近道です。
その道の専門家であれば、客観的な視点で様々な提案が期待できます。